自動売買の販売は投資助言・代理業にあたる?金融庁の登録要件や近年の投資詐欺を解説!
自動売買を販売する場合は、「投資助言・代理業」に当たるかどうかが重要です。
「投資助言・代理業」にあてはまると、金融庁の登録が必要になります。
金融庁の登録をしていないのに、自動売買の「投資助言・代理業」を行うと違法です。
しかし、どういった自動売買の販売が「投資助言・代理業」に当てはまるのか分からない方も多いでしょう。
本記事では、自動売買の「投資助言・代理業」にあてはまる条件から投資助言・代理業の違い、近年の詐欺について解説します。
「自動売買の販売がどこからどこまで投資助言・代理業にあてはまるのか知りたい」という方は、ぜひ参考にしてください。
詐欺を行っている会社の近年の手口なども公開しています。
目次
FXの自動売買の販売は投資助言・代理業にあたるかは状況次第

自動売買システムを販売する行為が「投資助言・代理業」に該当するかどうかは、販売形態や提供内容によって変わります。
単にソフトウェアを販売しているだけなのか、個別銘柄の選定や投資判断について助言を行っているのかといった点が重要です。
例えば、金融商品取引法において「投資助言・代理業」に該当するかどうかは、主に以下の要件が考えられます。
- 個別具体的な投資判断の助言かどうか
- 継続的なフォローやサポートの有無
- 投資家に代わる売買の代理行為の有無
それでは、具体的にどういった商品や行為が「投資助言・代理業」に該当するのか見ていきましょう。
個別に具体的な投資判断の助言かどうか
まずは、個別に具体的な投資判断を助言するのかどうかです。
単にプログラムの機能としての売買ロジックを提供しているだけであれば、「情報提供」とみなされる可能性があります。
しかし、投資家個人ごとにパラメータを設定する場合は、投資助言にあたるかもしれません。
また、特定銘柄や資産状況に応じた投資助言を継続的・具体的に行う場合は、投資助言業に該当することがあります。
つまり、個別に具体的な投資に関する指示がある場合は、「投資助言・代理業」にあたる可能性があります。
継続的なフォローやサポートの有無
システムの購入後に、フォローやサポートを行う場合は、投資助言になる可能性があります。
例えば、システムの購入後に、「こうやってエントリーしてください」「ここで決済してください」などが該当します。
つまり、販売だけではなく、投資判断に踏み込むコンサルティングのような行為は規制対象です。
商品購入後のフォローやサポートは、投資助言になる可能性があると覚えておきましょう。
投資家に代わる売買の代理行為の有無
投資家に代わる売買の代理行為は、投資助言・代理業に当てはまります。
自動売買システムが投資家の了解のもと、販売事業者側が投資家の注文を「代理」で実行する場合は代理業になる可能性が高いです。
代理業になると、単なる商品販売ではなく、金融庁による届けが必要となります。
投資の代わりにエントリー・決済、その他設定を行う場合は、代理業となります。
以上が、FXの自動売買の販売は投資助言・代理業にあたるかどうかです。
異国の戦士の見解としては、自動売買の単体の販売は「投資助言・代理業」に当たらないと考えています。
ただし、購入後にエントリー・決済の指示や代わりに取引を行うと、「投資助言・代理業」にあたります。
FXの自動売買を購入する上で、こういった法律面に関する知識なども知っておくと良いでしょう。
投資に関する法律の知識を知っておけば、どういった会社・サイトが違法なのかどうか判断できます。

自動売買の販売は、継続的なサポートや代理で取引すると、投資助言・代理業に該当するということですね。
そもそも投資助言・代理業って何?

FXの投資助言・代理業とは、簡単にいうとお客様の取引に対して、アドバイスや代わりに取引を行うことをいいます。
具体的なそれぞれの解釈は下記の通りになります。
| 投資助言と代理業の定義 |
|---|
| 投資助言業:投資判断に関する助言(具体的な銘柄や売買タイミングなど)を行う行為 代理業:投資家の代理人として、金融商品取引業者に注文を出すなどの取引執行を行う行為 |
投資助言は投資に関する判断をしたうえで、具体的な銘柄や売買タイミングを支持する行為です。
また、投資の代理行為は、投資家の代理人として、金融商品取引業者に注文を出すなどの取引執行を行う行為を指します。
例えば、「この通貨ペアで取引すべき」「このタイミングでエントリー・決済すべき」などが投資助言にあたります。
投資助言は取引に関するアドバイスをすることで、代理業は投資家の代わりに取引を行うことです。
投資助言と代理業の定義について詳しく知りたい方は、金融庁のホームページを確認すると良いでしょう。
金融庁の公式ホームページを見る▶

投資助言は具体的な銘柄やエントリー・決済のタイミングを教えることで、代理業は代わりにエントリー・決済を行うことです。
\期間限定!インジとEAを無料でプレゼント!/
投資助言と代理業と他の業態との違い

投資助言・代理業とほかの業態では違いがあります。
- 投資運用業(投資一任業務)との違い
- 情報提供ビジネスとの境界
今回は、投資と情報に関する観点から見ていきましょう。
投資運用業(投資一任業務)との違い
投資運用業(投資一任業務)との違いは、投資運用業が必要かどうかです。
投資助言・代理業はあくまで助言や代理注文が中心です。
一方で、投資運用業は投資家から預かった資産を、運用業者自身の裁量で売買を行う業務となります。
つまり、投資運用業はさらに踏み込んで顧客の資産を実際に運用するため、別途の登録区分(投資運用業)が必要となります。
投資運用業との違いは、別途の登録区分が必要かどうかで見分けましょう。
情報提供ビジネスとの境界
情報提供やビズネスの観点からは、継続的に助言するかどうかで異なります。
市況レポートやセミナーで一般的な情報・ノウハウを提供するだけなら、「投資助言」には該当しない場合があります。
しかし、個別の銘柄や取引手法について具体的・継続的に助言する場合は、「投資助言」に該当します。
例えば、下記のようなケースは助言にあたる可能性が高いです。
| 助言にあたるケース例 |
|---|
| 個別の銘柄や取引手法について具体的・継続的に助言する 対価を受け取る形で助言や指示を行う |
上記のケースは、投資助言・代理業の可能性が高くなります。

投資運用業は顧客の資産を実際に運用するので、資格がないと行えません。もしも、運用を行うと違法になります。
投資助言・代理業に関する法律はいつからあるの?
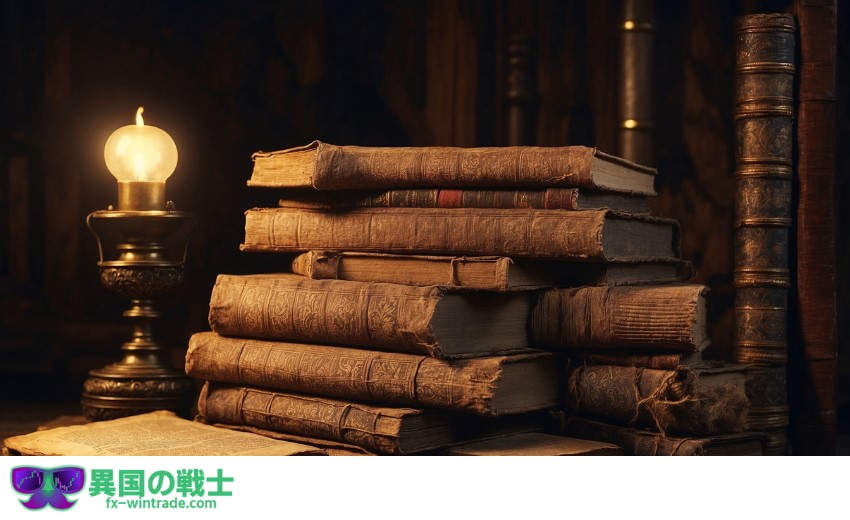
投資助言・代理業は、金融商品取引法(平成19年9月施行)により規定・監督されています。
投資家保護を目的に、投資助言を行う事業者に対して登録制・行為規制などが定められました。
もともとは、投資顧問業法(1986年施行)が制定されています。
投資顧問業法が制定されたことにより、投資顧問業を行う際には金融当局の許認可(登録)を受ける必要があります。
投資顧問業法から証券取引法等への統合・改正したことで、2007年に金融商品取引法に変更されています。
金融商品取引法への統合後は、下記のように種類が分かれています。
| 金融商品取引法への統合後の種類 |
|---|
| 第一種金融商品取引業 第二種金融商品取引業 投資助言・代理業 投資運用業 |
金融商品取引になってからは、合計4つの種類に別れています。
金融商品が第一種になったことで、投資に関する助言や代理業は、金融庁の登録が必要だと覚えておきましょう。
投資助言・代理業に関する法律は1986年から制定され、2007年に金融商品取引法に変更されています。

FX取引は1998年に外国為替および外国貿易法の改正で外為業務が自由化されたことに伴って始まった金融商品なので、投資の歴史で考えると金商品取引法の制定も最近ですね。
金融庁に登録する際の登録要件と規制

金融商品に登録するためには、金融庁の登録条件と規制を理解する必要があります。
では、金融庁の登録に必要な登録条件と規制は下記の通りです。
| 金融庁の登録に必要な項目 |
|---|
| 資本金や財務基盤 内部管理体制 行為規制 |
金融庁の申請を突破するには、財務状況と内部管理体制がしっかりしていないといけません。
また、金融庁に登録した会社には、さまざまな規制などもあります。
| 金融庁に登録する際の義務化されている内容 |
|---|
| 誇大広告の禁止 手数料やリスクの開示 利益相反の開示・管理 |
金融庁に登録した会社は、誇大広告の禁止をかかげています。
また、手数料やデータの適切な開示なども義務付けられていることが多いです。
つまり、金融庁に登録している会社は、各さまざまな条件をクリアしたうえで登録することが可能です。
金融庁に登録するためには、資本金や財務基盤、内部管理体制がしっかりしているかどうかが求められます。
以上が、金融庁に登録する際の登録要件と規制です。
金融庁に登録するにはさまざまな要件をクリアする必要があるため、クリアしている会社は安全性が高いです。
もしも、サイトや会社で金融商品を購入する際は、金融庁の登録があるかどうか確認して見ても良いでしょう。
無許可で自動売買の投資助言・代理営業を行っている会社が存在する
実は、近年金融庁の登録をしていないにもかかわらず、投資助言・代理営業を行っている会社・サイトが増えています。
SNSでは「オンラインサロン」という投資コミュニティーを設けて、無許可で投資助言・代理営業を行っている傾向があります。
例えば、「指示に従ってエントリー・決済するだけ!簡単に稼げる!」の広告で、あなたにとって都合の良い言葉をかけてきます。
甘い誘惑にのってしまった結果、詐欺に被害にあう可能性があるため、十分にご注意ください。
特に、2024年以降『tiktok』は、『Instagram』、『Facebook』を抜いて被害件数が多くなっているため、慎重に行動しましょう。
近年は、SNSで金融庁に登録していない会社が、詐欺を行っていることがあるので、購入する前に会社の基本情報を確認しましょう。
特に、金融庁の登録をしているかどうか確認することで、詐欺防止につながります。

金融庁の登録は、会社の資本金や財務状況、商品に関する広告などを見て判断されます。つまり、金融庁の登録している会社はある程度健全な会社のため詐欺にあう確率が低くなります。
まとめ
自動売買システムを販売する行為が「投資助言・代理業」に該当するかどうかは、販売形態や提供内容によって異なります。
また、ソフトウェア単体を売っているのではなく、継続的な助言及び代理の取引を行うと「投資助言・代理業」に該当します。
「投資助言・代理業」に該当する場合は、金融庁に登録する必要があります。
金融庁に登録する際には、資本金や財務状況、その他規制を守れなければいけません。
近年、SNSを中心に金融庁の登録なしに、自動売買や裁量トレードを使った「投資助言・代理業」が増えています。
特に、tiktokはSNSの中でも被害件数が非常に多いため、いきなり広告・メールが来ても無視するのが一番です。
もしも、自動売買や裁量トレードに関する「投資助言」を行ってもらう場合は、金融庁の登録があるかどうか確認しましょう。
金融庁の登録をしている会社は、ある程度信頼性が高いといえるため安心といえます。
FXの自動売買システムの「投資助言・代理業」を理解することで、詐欺防止にもつながります。
ぜひ、この機会に投資の「投資助言・代理業」について覚えておきましょう。
\期間限定!インジとEAを無料でプレゼント!/

2014年駒澤大学経営学部・経営学科卒業。その後、SEOを中心に事業を営む会社でコンテンツマーケティングを経験。コンテンツSEOを中心に各種プロジェクトに参画し、個人ではFXトレードを経験。株式会社セネリアスでは、半年間で表示回数・クリック数を倍にすることに成功。コンテンツSEOの豊富な知識や丁寧な対応、自身で経験したFXの経験をもとにユーザーファーストを心がけたライティングが強み。
【異国のAI爆益祈願フェス】が開催!
新作のAIボリバンが10,000円OFF!

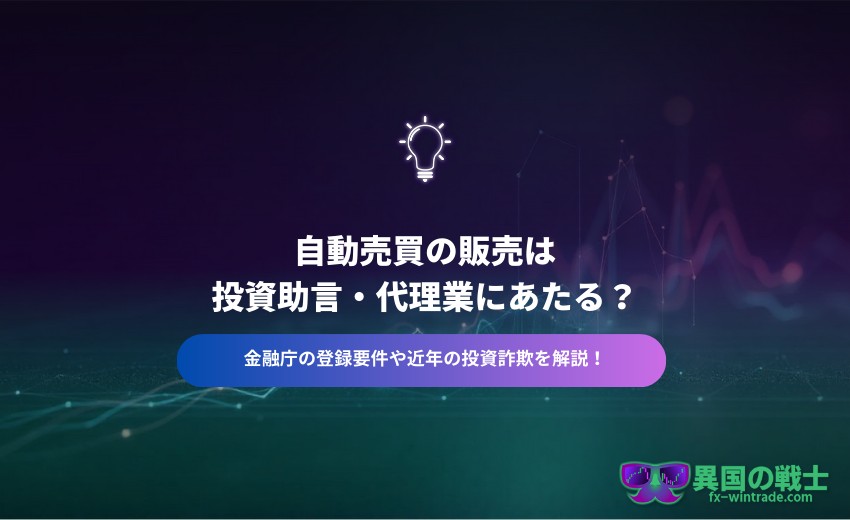

コメント
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。